スポンサーリンク
先日ちょっと気になる情報を耳にしました。
『ハチミツはアーユルヴェーダでは「痩せ薬」的な役割を果たす』
というものです。

↑この記事で紹介したやつですよね。これは割と「西洋医学」に基づいたお話でした。
でも今回のテーマのアーユルヴェーダは、「インド発祥の伝統医学」の考え方に基づいていて、また違った切り口でハチミツの健康・ダイエット効果を定義しているんです。
まったく性質の異なる医学の見地で面白いと思ったので、今回は『アーユルヴェーダにおけるハチミツの役割や効果』についてご紹介しようと思います。











アーユルヴェーダとは


人によってはエステのようなイメージかもしれませんが、アーユルヴェーダはインド・スリランカ発祥の5千年以上続く、れっきとした伝統医学です。
ギリシャ・アラビア発祥のユナニ医学、中国医学と並ぶ世界三大伝統医学の一つで、『ヴァータ』『ピッタ』『カパ』という3つの要素が生命活動を支えているという考えが基本にあります。
- ヴァータ:風(運動エネルギー)
これが増大しすぎると、呼吸器系疾患、精神・神経疾患、循環器障害を起こす。 - ピッタ:熱(変換エネルギー)
これが増大しすぎると、消化器系疾患、肝・胆・膵疾患、皮膚病を起こしやすい。 - カパ:粘液(結合エネルギー)
これが増大しすぎると、気管支疾患、糖尿病、肥満、関節炎、アレルギー症状を起こしやすい。
参考:Wikipedia|アーユルヴェーダ
アーユルヴェーダの医師は診察をして、これらどの要素に強弱があるかを判断して、緩和療法(食事療法や薬の処方)や、減弱療法(デトックスみたいなイメージ)といった治療を行います。
そして緩和療法の食事療法において、カパが強い場合にハチミツを処方するんだそうです。
こうして見ると、肥満にはハチミツを処方する⇒痩せ薬として扱われている、というのもあながちデタラメじゃない気もしますね!
ちなみにエステで行われるアーユルヴェーダのマッサージは、減弱療法の一種で「薬草(主に温かいごま油)でマッサージをすることにより、薬草の抗酸化作用で発汗を促す」といった所から派生したものですが、観光客向けにかなりアレンジされているらしく、本来の「治療」という意味合いはないみたいです。











一般的に言われるハチミツの効果・効能


では次に、世間一般で言われているハチミツの効果・効能について見てみましょう。
ここでは詳細な説明は割愛するとして、どんなものがあるか?だけ軽くご紹介しますね!
| ハチミツの効果・効能 | 具体的に期待できる健康・美容効果 |
| 殺菌・抗菌作用 (細菌やウイルスをやっつける、または活動を抑制する) |
|
| 保湿効果 (ハチミツの高い吸湿性(水分を吸収・維持する働き)) |
|
| 抗酸化作用 (ハチミツに含まれるミネラル類、ポリフェノールなどの抗酸化成分) |
|
| 栄養バランス (ビタミンB群やビタミンC、酵素、アミノ酸などが含まれている。単糖類による体へのエネルギー補給) |
|
こんなところでしょうか。
もちろんハチミツの種類によって、これらの効果が発揮される強弱には差があります。
アーユルヴェーダではどんなハチミツを選べといいかは後述することにして、こうやって具体的な効果・効能をみてみると、アーユルヴェーダの説明のところで挙げた「カパ」が増大したときに起こりやすくなる疾患と重なる部分がありますね!











スポンサーリンク
アーユルヴェーダにおけるハチミツの役割


さて、ここまでアーユルヴェーダとは何か?ハチミツって健康にどんな効果があるのか?について簡単に(本当に簡単に)紹介してきました。











ハチミツ食べれば痩せるっていうのがアーユルヴェーダ的な見方じゃないの?
それがそんなに単純なハナシじゃないんです。。。
本来のアーユルヴェーダは『医療行為』であり、ハチミツの処方は薬の処方と同じです。
むやみやたらに食べればいいってものじゃないんです(ここ重要_〆(゚▽゚*) )
確かにアーユルヴェーダ的には肥満にはハチミツを処方するようですし、それが「痩せ薬」だとする見方もできると思いますが、同時にハチミツは「処方される薬」なのです。
安易なハチミツの摂取は禁物ということですね!
と、いうことで次は「じゃあ、どんな風にハチミツを摂取すべきか」について少しご紹介します。











ハチミツを摂るときのルールや注意点


ここではアーユルヴェーダにおけるハチミツ摂取の方法をかなり簡略化してご紹介しています。アーユルヴェーダ専門医の監修などは受けておりません。
「安易に手を出しても効果がないんだな」というご認識をいただく程度の読みものとしてお願いいたしますm(_ _)m
ハチミツに熱を加えない
まずこの一言に尽きます。
これを聞くと人によっては、
「非加熱のハチミツがいいんだね!」
と早合点してしまうかもしれませんが、実はそれだけではありません。
アーユルヴェーダでは過剰な熱を与えるのは「アーマ(毒素)」が増大するので良くないこととされています。
つまり、ハチミツ生産時に加熱しているのはもちろんNGですが、加熱料理に使ったり、風邪などで発熱があるときに食べたり、運動して体温が上がっているときに食べたりもNGなんです。
NGな例を少し列挙してみると、、、
アーユルヴェーダ式ハチミツNG集
- 生産時に加熱されたハチミツ
- 輸送時や店頭陳列時に高温にさらされたハチミツ
- 夏場に摂取する
- 冬場の暖房がきいた部屋で摂取する
- 体調不良で発熱しているとき摂取する
- 運動をして体温が上昇しているときに摂取する
- お風呂上がりに摂取する
- 加熱料理に加える
- コーヒーや紅茶などのホットドリンクに加える
などなど、他にもかなりNGなパターンがありそう。。。
とりあえずハチミツの選び方としては、国内産(できれば直販売)の非加熱ハチミツを選ぶのがなんだか良さそうです。











バターオイルと一緒に摂らない
アーユルヴェーダに少し詳しい人なら、日常的にバターオイルを使っているかもしれません。
バターオイルはアーユルヴェーダでいうところの「ピッタ」(増大しすぎると、消化器系疾患、肝・胆・膵疾患、皮膚病を起こしやすいとされる)が多すぎると診断された場合に処方されるものです。
そしてアーユルヴェーダの古典書には
『ハチミツと同量のバターオイルを混ぜると死を招く』
という文言があったりするそうです(恐)











スポンサーリンク
まとめ
少しガッカリさせてしまったかもしれませんね。。。











ですね。
『アーユルヴェーダ専門のお医者さんからの処方があればこそ効果を発揮するもの』
というのが今回なんとなくわかりました。
調べる中で、本屋さんなどで購入できるアーユルヴェーダの本には、「非加熱ハチミツならOK」というくらいしか書かれていないものが多いのも驚きました。
確かに非加熱ハチミツなら、ハチミツ本来の栄養素が破壊されていないので、健康への期待値は高いんですけども。。。
兎にも角にも、今回、アーユルヴェーダへの認識が私も大きく変わりました!
なんでも突っ込んで調べてみるものですね!











スポンサーリンク
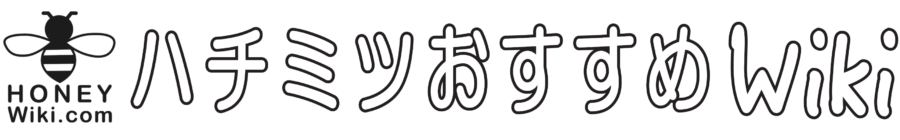













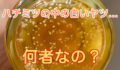








寝ている間に成長ホルモンの分泌を促進するとかのハナシかな?